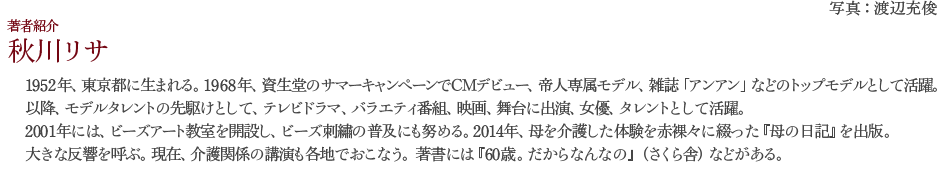第16回
2度の戦争を経験した祖母
私は、明治生まれの祖母に育てられた。
彼女は、仙台の呉服屋さんの家に生まれた8人兄妹の4番目の子どもで、幼い頃に兄と妹を病で亡くしたそうだ。
明治28年(1895年)の生まれで、小さい頃に日露戦争を経験したという話を、私によくしてくれた。
「本土決戦もなく、日本は勝ったって、みんな喜んで、提灯行列とか派手にやってたけど、どれだけの人が死んで、どんだけの未亡人ができてしまったか。
乳飲み子抱えて苦労した人をたくさん見たからね。
戦争はよくないよ。若い人間をたくさん殺してしまう。
でもね、あの頃は婦人参政権もなく、女が戦争反対なんて言える時代じゃなかった」
そして、彼女は40代で2度目の戦争を経験した。
「2度も戦争を経験するなんて、やだね〜。
結局あの時も、反対とか、声をあげられなかった。
でもね、私がいちばん可愛がっていた弟は、とっても優秀な子でね。
できたばっかりの東北帝大に入って、自慢の弟だったんだよ。
繊細で優秀な子だった。
体が弱くって、戦争とかに駆り出されなくてよかったけど、戦争に突き進んで行った日本を悲観したのかねぇ。
自殺しちゃったんだよ。
今でも、本当の理由はわからない、なんで死んだんだか。
戦争がなかったら、生きていたんだろうか?
戦争は嫌だ。たくさんの人間の生活や生き方を壊してしまうから」


その祖母の人生も、波乱万丈だった。
17歳で 親の決めた相手と 結婚をした。
「父親は、女に学問はいらないって言ってね。
小さい頃は、日本舞踊や三味線とか、習い事はさせてもらえたんだよ。
あの頃はまだ、呉服屋もうまくいってたんだろうね。
でも、だんだん傾いてきたのは、なんとなくわかったね。
尋常小学校に行って、高等小学校までは行かせてもらえたんだけど、私は勉強がもっとしたかったのに、
『女は家事手伝いをして、お嫁に行け』
って父親に言われて、会ったこともない人のところに泣く泣くお嫁にいったのよ。
津田塾に通うのが、あの頃の夢だった」
祖母は、本を読むことが好きだった。
「お嫁に行った先は、意地悪な小姑やきついお姑さんがいてね。
『本読んでる暇があるくらいなら、ちゃんと掃除くらいしたらどうなんだい。呉服屋の娘は、赤い腰巻チラチラさせて雑巾がげもろくにできない』
なんて言われて、3年で、こっちから三下り半突きつけて、家を出たの」
その後、祖母は東京に向かった。
「出戻り娘が帰れる実家なんてないからね。
本当は学校に通いたかったけれど、お金もないし、子どもの頃に身につけた日本舞踊と三味線で身を立てようって思って、新橋の芸者置き屋の門を叩いたの。
芸は身を助けるって、よく言ったものね。
お蔭さまでいっぱしの芸者になれたもの。
今はおばあちゃんだけど、若い頃は仙台小町って言われたくらい綺麗だったんだよ、 私」
祖母の芸者時代の写真は、当時の絵葉書にもなっていて、本当に綺麗だった。
残念ながら、今、その絵葉書は行方不明だが、きっと家のどっかから出てくることを期待したい。
祖母の2度目の結婚生活も波乱万丈だ。
「おじいちゃんとはね 金田中(大正時代創業の新橋の花街にあった料亭)であったのよ。
三木武吉さん(政治家)付きの新聞記者だったの。
30歳で身ごもったから(私の母を)、芸者をやめておじいちゃんと一緒に暮らし始めたんだけど、福井に本妻さんがいてね。
本妻さんが亡くなられた後、あちらのお子を引き取って、後添いに入ったの。
あんたのお母さんの名づけ親に、三木武吉さんがなってくださってね。
あの頃は、政治家や仕事ができる男には、お妾さんがいるのは当たり前、それが男の甲斐性みたいな時代だったからね。
でも、あの頃がいちばん幸せだったかなぁ。
千葉に小さな別荘もあって、毎年夏には、そこで暮らして楽しかったわねぇ。
でも、その別荘も、戦争が始まると、本土決戦の時は千葉から米軍が上陸するっていう噂が立って、女・子どもは何されるかわからないから、売ったほうがいいってことになってね、二束三文で 売っちゃったのよ。
もったいないことしたわねぇ」
祖母の幸せの時代も、戦争によって長くは続かなかった。
「おじいちゃんは、戦争に負けたら、もう自分の人生も負けたみたいに思ったんだろうね。
戦争中は、書きたくない記事も書いたからね。
負ける戦争とわかっていても、もう戦争を止めようと思っても、そんなこと書いたら、 憲兵さんに引っ張られるもの。
福井空襲で、実家が半分燃えて、その後処理に行ったきり、東京には帰って来なくなった。
でもね、戦争に負けてよかったこともあるんだよ。
アメリカさんが来て、憲法を変えたことで、女にも参政権がもらえたし、昔に比べたら、 女が働くことだって、どう生きたいかだって、選べる時代になったんだから。
アメリカさんが来たから、あんたも生まれたんだから」
明治生まれの祖母は気丈な人で、進歩的な人でもあった。
平塚らいてう(戦前戦後の女性解放運動家)、与謝野晶子、市川房枝さんを尊敬していた。
「女もね、これからは学問で身を立てるか、手に職を持って、生涯働いていく時代だよ。
男に頼ったって、またいつ戦争が起きて、死んじまうかもしれない。
泣いて我慢するより、自分の人生は自分の手で開くんだよ。
でも、男社会を日本はなかなか変えられないだろう。
意外と男は小心者、自分に自信のない男ほど、女の前で威張りたがる。
そんな男には腹立てず、手の上で転がしておやり。
女はね、利口ぶっちゃだめだよ。
馬鹿なのに利口ぶる女ほど、みっともない女はいないからね。
本当の利口は、バカな振りができる人さ。
知性と想像力を持って、自分の生きる場所をつくりなさい。
女だからだめだなんてことは、何一つない。
男はなかなか変われないから、女が変わっていくのよ。
でもね、一つだけ注意しなければいけないことは、女の足を引っ張るのは女だっていうこと」
明治・大正・昭和と生き、2度の戦争を経験したおばあちゃんの教え、肝に命じて、これからも、生きていきます。