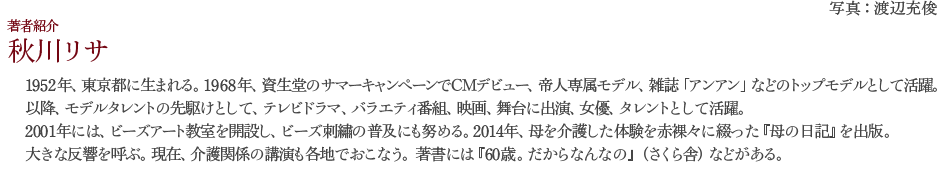第26回
シェアハウスPART2
2011年4月、娘に、
「ママ、シェアハウスを始めるわ」
と言うと、
「無理、無理、絶対。ママ、自分の性格、わかっているでしょう。
ママは他人に厳しい人でしょう。そんな人が、シェアハウスなんて無理」
と言われた。
息子にも、
「世の中いい人ばかりとは限らない。
変な人にでも入って来られたら、夜もおちおち寝てもいられない。
シェアハウスなんてやめときなさい」
と言われた。
それでも、私は不動産屋さんにシェアハウスを始める下準備をしてもらっていた。
娘から電話が来た。
「知り合いに、ママがシェアハウスを始めるみたいって言ったら、『そんなにあなたの実家、お金に困ってるの』って言われたわ。
そうなの? お金に困ってるの? 仕事うまく行っていないの?
だったら、私やお兄ちゃんに相談してよ。手助けできることもあるんだから」
そうか。シェアハウスを始めるというと、お金に困ってという発想を持つ人もいるのかと初めて気がついた。
空いている部屋を貸して、お金も入ってくるのは決して迷惑なことではない。
むしろありがたいことだが、私のいちばんの目的はそれではなかった。
外国から日本に働きに来る人や、日本の文化や日本語を学びに来る留学生たちが、ちゃんとしたビザを持っていても、なかなか部屋を借りられない。
あるいは不動産屋によっては、外国人はお断りというところもあると、当時(2011年)結構多くの人から聞いていた。
9・11アメリカ同時多発テロ事件以降、特に中東の人たちや回教圏の人たちはどこの国でも部屋や家を借りづらくなってきている時期だった。
実際に、娘の大学時代の同級生でドバイから日本の文化を学びに来た青年に、日本人の保証人がいないとお金はちゃんと払えるという証明書を出しても部屋が借りられないという相談をされたこともあった。
今でこそ、誰でもシェアハウスがなんであるかは知っているし、ドラマにもなったくらいだから、その上、民泊の家も近所に増えて、スマホ片手に民泊の住所を探しながら荷物を引っ張っている外国人を多く見かけるようになったが、当時(2011年)はシェアハウス自体まだ、日本には馴染みも薄く、都内の件数も少なかった。

「シェアハウスを始めるよ」
と知り合いに声をかけると、すぐに借り手が1人見つかった。
不動産屋さんに、1人は見つかったので、あと3人募集してほしいと連絡を入れると、
「大家さんからの、なにか住人さんにメッセージはありますか?」と聞かれた。
「性別・国籍・宗教・LGBT一切問いません。いつか、アカデミー賞かノーベル賞を取ろうと思っている夢のある方歓迎します」
私は本気でこう言ったのだが、不動産屋さんには一笑に付されて、このコメントは使われなかった。
最初の住人さんは、政治家を目指し政治塾に通っている日本人青年、香港から日本の商社に働きに来た女性グラフィックデザイナー、その友人で外資系金融会社で働く台湾人の女性、英語の先生をしながらアニメーションの通信教育を受けているオーストラリアの青年(後日書くけれど、彼は今、アメリカのアニメーション会社でチーフになって、本気でアカデミー賞を狙っています)。
2011年4月、4人の同居人が決まり、シェアハウスが始まった。
私も正直、他人と暮らすというのは、娘が言うように、私には向かないかもしれないという不安がなかったわけではないが、違う発見や喜びもあるのではないかという期待もあった。
そして、意外や意外、私は他人と暮らすのに向いていた。
家族なら、帰りが遅いと心配したり、玄関の靴の脱ぎ方が雑でイラッとしたり、部屋の掃除はちゃんとしているのかなど、いちいち気になって、わが子ゆえに口出しをしてしまっていたが、シェアハウスの住人は他人様。
他人様には他人様のやり方があり、性格も違う。ましてや、国も違うから、文化や考え方も違う。
ほどよい距離感を保つことで、イラつくこともなかった。
むしろ、誰かが帰ってきたなと、玄関の鍵を開ける音でホッとしている自分に気がついた。
強がっていても、ひとりで暮らすということに、私は寂しさや孤独感を感じていたのだと思う。
それを、家に誰かがいるという気配で、私はひとりじゃないという安心感を持つことができた。
週末には、住人さんたちみんなで、ご飯会をするようになった。
もちろん、参加・不参加は自由で、強制ではない。
でも、当時の住人さんたちはとても甘え上手で、週末に調理に腕を振るう私を調子にのらせてくれた。
「おいしい、おいしい」と言って、みんなでテーブルを囲み、今週は会社でこんなことがあったけれど、これは日本独特な考えなのか?と聞かれたり、日本の有名な祭りに行きたいがどこがいいかと、みんなで調べたり、来週は友人も呼びたいが一緒にいいかと言われ、 気がついたら週末10人は一緒にご飯を食べることが当たり前になっていった。
それぞれの情報交換をする場所にもなり、住人の友人が違う住人の友人になり、その輪が広がっていった。
私は寮母のような立場を大いに楽しめるようになった。
国籍の違う文化の違いで、時に戸惑うこともないことはなかったが、国籍や言葉の違いや文化の違いより、最終的にはその人の人間性が素敵なら、大抵のことは許せるものだと思えるように私はなっていった。
娘と息子が、たまにご飯会に加わるようになり、
「ママがこんなに、シェアハウスに向いてるとは思わなかったわ。楽しそうでよかった」
と娘が言えば、息子は、
「うちの母の生存確認、今後も住人のみなさま、よろしくお願いします」
と言って、みんなを笑わせて帰って行った。